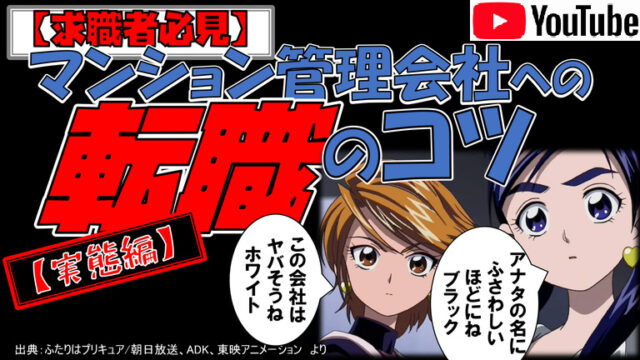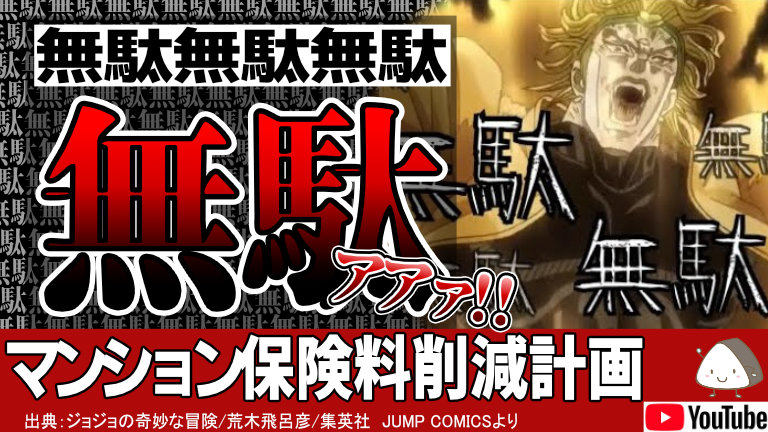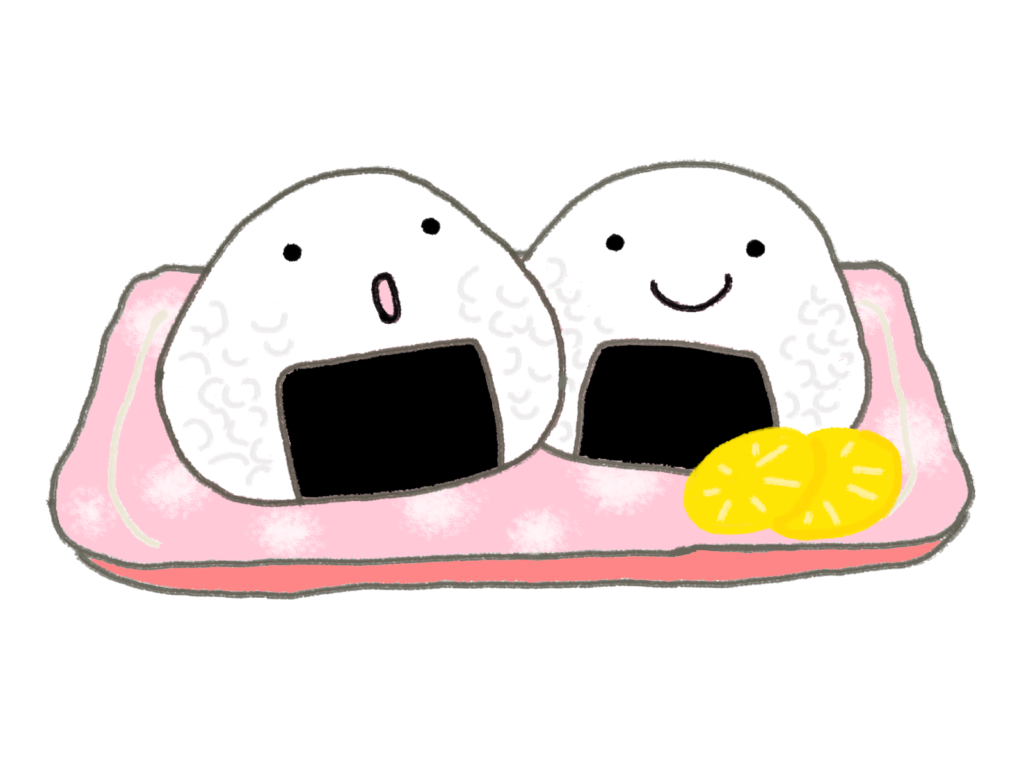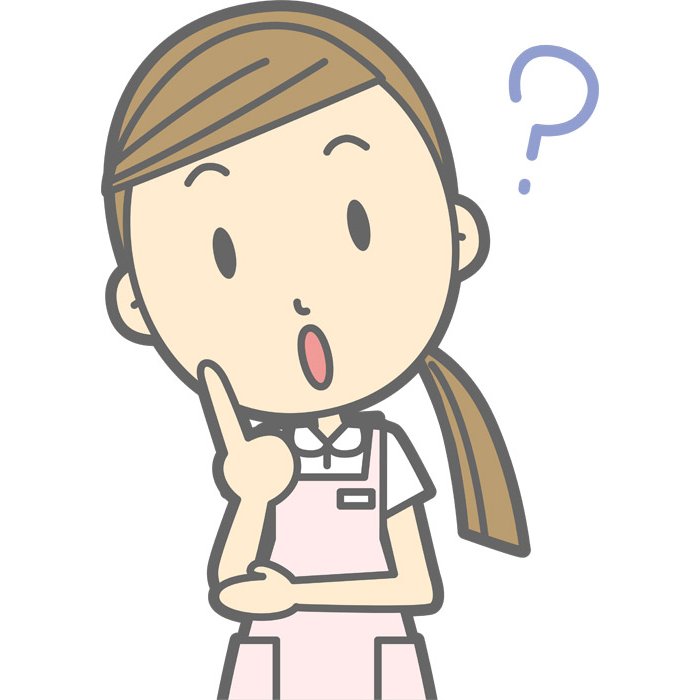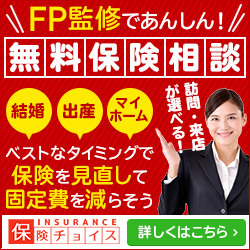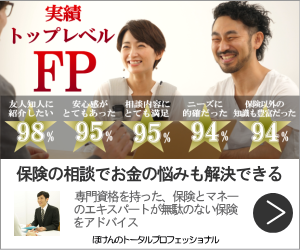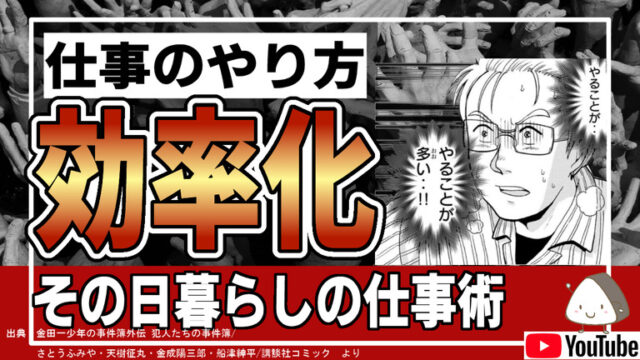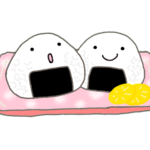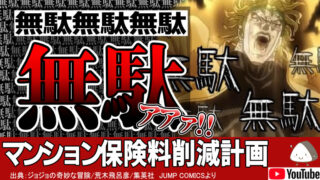- なんでこんなに保険料が高くなるのか。
- もっと保険料を抑えることはできないのか。
- そもそもマンション保険って何に使うの?
▼コチラ▼の前半記事では「マンション保険の中身」についてご紹介しました。

この後半記事では自分のマンションにあったオリジナルの保険プラン構築ノウハウについて徹底解説します。
『オリジナル保険プラン作成の道』の結論
簡単に結論をまとめると次のとおりです。
それでは内容について、細かく見ていきましょう。
この記事では、マンション管理組合が加入する保険を全部をひっくるめて「マンション保険」と表現しています。
保険の内容の説明をする際は、保険会社ごとに保険商品名や補償内容を名称まで正確に伝える必要があることは承知してますが、記事の特性上、読まれる方の分かりやすさを重視して、あえて「マンション保険」と表現していることをご了承ください。
オリジナルのマンション保険作成のノウハウ!
保険の補償内容を見直す前に
保険プランの見直しを考える上では、
- 頻繁に使う補償内容はそのままに
- 使わない補償内容は削除して
- 発生確率が低い被害は要検討
こういうコンセプトで検討するのが望ましいと思われます。
補償内容見直しのポイント
補償内容ごとの判断ポイントは次のとおりです。
【加入必須の補償内容】
《基本補償》(個別で付け外しはできないので1セットとして考える)
 |  |  |  |  |  |  |
- 火災・落雷・破裂・爆発・風災・雹(ひょう)災・雪災
- 外部からの物体の落下、飛来、衝突
- 騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為
- 盗難による盗取、損傷、汚損
- 対象建物内(共用部分内)の盗難
- 損害防止費用補償
《特約》
 |  |  |
- 水濡れ損害補償特約
- 水濡れ原因調査費用補償特約
- 破損・汚損損害等補償特約(電気的・機械的事故補償以外)
ここがポイント!
- マンションの保険申請は「漏水」「破損汚損」が大部分を占めます。
- 破損汚損は築年数関係なく発生するリスクがあり、漏水は高経年マンションだとかなり高い確率で発生するため、マンション保険では必須といって良い補償プランです。
【できれば加入したほうがいい補償内容】
《特約》
 |  |  |
- 臨時費用補償特約
- 個人賠償責任特約包括契約に関する特約
- 施設賠償責任特約
ここがポイント!
- 『臨時費用補償特約』は、もらえる保険金に+10%を上乗せしてもらえる特約です。これにより被害額より多く保険料をもらえることがあります。保険料自体もそれほど高くないので、入った方がお得です。
- 『個人賠償責任保険』は、居住者が個々に加入しているケースが多いので、保険料削減のネタにされやすい補償ではありますが、マンション総合保険では1件当たり月額80~90円と相当安い(個別加入したら1人あたり月額200~300円位)ので、総合的に考えるとマンション保険として加入した方がオトクです。
- 『施設賠償責任保険』は、外壁タイルの落下や、マンション共用排水管から専有部分へ漏水など、管理組合の建物・設備の老朽化や思わぬ事故で役立つ保険です。役立つシーンはあまりありませんが、いざ被害が出た際には1被害がかなりの金額になるケースがありますし、保険料自体全体の割合からみればそれほど高額でないので、加入することをお勧めします。
【加入するか判断が分かれる補償内容】
 |  |  |  |
- 地震保険
- 地震危険等上乗せ特約
- 水災補償特約
- 破損・汚損損害等補償特約(電気的・機械的事故補償)
ここがポイント!
- 『地震保険』は、近い将来必ず起こると言われている、来るべき大震災への備えです。「あった方が良い」補償ではありますが、地震保険に加入すると保険料が2倍以上に跳ね上がるので、非常に判断が難しいです。
- 『地震危険等上乗せ特約』は、補償額が少ない地震保険の不足分をカバーする特約です。「保険料が上がっても地震保険に入る!」と腹をくくった管理組合なら、こちらも入ることをお勧めします。
- 『水災特約』は水害対策のための特約ですが、前編で紹介したとおり「床上浸水or建物全体の30%以上の損害」がないと補償されません。床下浸水は補償されませんし、保険料もかなり高めなので、床上浸水のリスクがない(もしくはそのリスクが少ない)マンションはお勧めしません。
【ぶっちゃけいらない補償内容】
 |  |  |  |
 |  |  |  |
- 凍結水道管修理費用保険金
- ドアロック交換費用保険金
- 仮住まい費用保険金
- 地震火災費用保険金
- 失火見舞費用保険金
- 類焼損害特約
- 宅配ロッカー内動産補償特約
- 管理組合役員対応費用補償特約
ここがポイント!
- 『凍結水道管修理費用補償金』は、寒冷地でない限りほぼ出番がないので無駄です。
- 『ドアロック交換費用補償金』は、鍵をちゃんと管理してれば出番はありません。
- 『仮住まい費用保険金』は、条件がキツ過ぎて適用されたケースを見たことないほどレアです。
- 『失火見舞費用保険金』は、被害補償ではなく見舞金に充てるためのものです。上限も1事故20万円と低く、そもそも発生確率の低い事案の見舞金に保険に入ることはナンセンスなので、入っても無駄です。
- 『類焼損害特約』は、もらい火を補償する保険です。基本補償の火災保険は延焼の被害補償は対象外ので一見有用そうですが、そもそも「共用部分が火元になる火災」自体がかなりレアケースなので、入ってもほぼ出番がないように思えます。
- 『宅配ロッカー内動産補償特約』は、届け物を補償する保険です。そもそも何で個人宛の荷物を管理組合が金を出して補償しないといけないのか、という議論になるのでムダです。
- 管理組合役員対応費用補償特約は、訴訟されそうな理事会や、長期滞納者の法的措置(訴訟)を起こそうとする際に使えます。これもかなりレアケースですので、毎年保険料を払うほどのことではない気がします。
出典:掛捨型マンション総合保険パンフレット(2021年1月版)[PDF]/損保ジャパン
マンション保険にはたくさん補償内容があるけど、使う保険は限られてるよ!
特に『水災補償特約』は、適用条件も知らずに漠然と入っているマンションが多いから、ちゃんと見直そうね!
補償内容カット以外での保険料削減の方法
補償内容の見直し以外にも、保険料を削減する方法は次のとおりです。
1.長期契約
マンション保険は通常1年契約ですが、5年の長期契約にすると保険料はある程度割引されます。
長期契約にした場合、保険料の割引を受けられるほか、保険料率の改定などで保険料が上がっても、契約期間中なら追加保険料を支払う必要がない、というメリットがあります。
2.保険の付保割合の低減
マンション保険の保険料は建物価額に基づいて計算され、その建物価額は『建物の再調達原価(新価)』×『付保割合』によって導き出されます。
付保割合を100%にすれば、建物を建て直すレベルの保険を掛けることができますが、そもそも鉄筋コンクリート造の建物が100%破壊されるなんてことは想定されないので、付保割合(保険を掛ける割合)を下げて保険料を圧縮する、という方法があります。
多くのマンションは60%程度で設定していますが、「発生確率を考えて、毎年多額の保険料は支払えない」と考えるマンションでは、付保割合を30%に下げ、保険料を削減しています。
多額の被害が想定されるケースは、恐らく『火災』です。付保割合を考える際には、「このマンションで火事が起こったら、一体どのくらいの被害が出るだろうか」ということを主眼に、保険の付保割合を考えるといいでしょう。
3.優良物件割引の適用
保険会社によっては「一定期間保険金を受け取らなかったマンションは、『優良物件』とみなして次の更新時に割引するよ」という制度があります。
これを適用する/しないで、保険料が20~25%も変わってくる場合があるので、保険金の受取時期を調整するなどして、是が非でも割引を受けるようにしましょう。
4.自己負担額(免責金額)の増額
もらえる保険金は、次のとおりの計算式で産出されます。
【もらえる保険金】=保険認定額-自己負担額+各特約(※)
(※臨時費用補償特約、残存物片付け費用などの上乗せ金)
原則としては認定を受けた保険金額+追加した特約などの上乗せ金をもらえるのですが、「自己負担金(免責金額)」を設定していると、その分保険金額からマイナスされます。
つまり「自己負担額(免責金額)」は、「保険加入者が自分で負担する範囲ね」というふうに設定された金額で、これが設定されることにより、もらえる保険金が減ってしまいますが、代わりに保険料を安くすることができます。
『設定金額10万円』など、自己負担額を高めに設定すればするほど保険料を削減できますが、いざ保険申請をする際、その自己負担額分は自分たちの財布から出さなければなりません。
保険申請をそれほど行っていないマンションなら有用ですが、保険事故申請(特に10万~1万円程度の小規模の保険事故申請)を頻繁に行っているマンションには不向きと言えるでしょう。
5.建物価額の低減
上記2で「付保割合」を低減することで保険料を削減する方法をご紹介しましたが、マンションの建物価額そのものを低減させる方法もあります。
しかしこの方法は、本来あるべき建物評価を、保険料軽減のためだけに変更しようとする行いですので、個人的にはあまりお勧めしません。
保険各社への相見積
補償内容が決まったら、保険各社に見積を依頼しましょう。
保険会社でそれぞれ細かな約款や契約条件が異なるので、全く一緒の見積を作ることはできない場合が多いですが、似たようなプランを各社用意していますので、ある程度の見積比較は可能です。
会社によって同じ(ような似た)補償内容でも、金額にかなり開きがあるケースが多々あります。保険料削減をしたいと考えるなら、必ず2~3社の相見積を取りましょう。
同じ保険会社で相見積を取ったら、同じ条件で相見積を取れるんじゃない?
このような事をよく言われます。誤解されている方も多いのですが、
同じ保険会社なら、どこの代理店で見積を取っても金額は一緒です。
保険の見積は修繕工事のように、物代、手間賃、交通費など、修繕工事をする会社ごとに単価を設定しているわけではなく、保険会社が作る見積を代理店がそのまま提出しているだけにすぎません。
ですので、保険の相見積を取ろうとするなら、同じ保険会社で取っても無駄ですので、別の保険会社をあてがうしかありません。
保険カットはノーガード戦法
補償内容の削減や、保険の付保内容を下げるなど、保険料削減の方法はいろいろあります。
ですが、そもそも保険は『将来の安心をお金で買う』という行為です。
逆に言えば、保険料削減のために保険プランを削減する行為は『お金のために将来の安心を切り売りする』という行為に他なりません。いわばノーガード戦法です。
確かに限りある管理費は大事に使っていかなければなりません。
ですが、マンションに住む人が安心して暮らし続けるための先行投資と考えることもできます。
マンションに関わる人の理解を得ることが非常に重要になってきます。保険プラン削減を行おうとする際は、説明会を開くなどし、できるだけ多くの賛同を得た上で進めるよう心がけましょう。
まとめ!
ここまでの内容をまとめてみましょう。
『オリジナルの保険プラン策定』についてまとめると次のとおりです。
ではこのへんで。かわぐちろろでした。
かわぐちろろ の【ろろ余談】
安心を取るか、お金を取るか。
起こるかどうか分からない災害のために多額の資金を投じるか。
非常に悩ましい問題ですね。