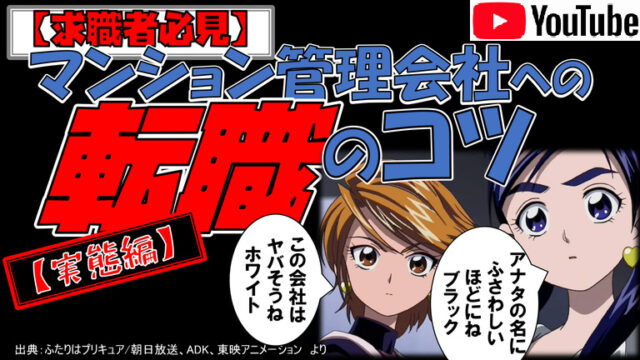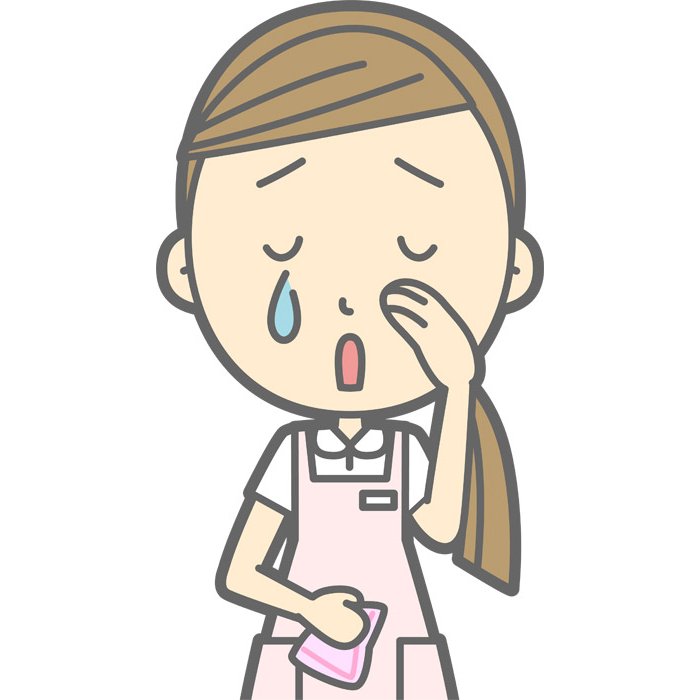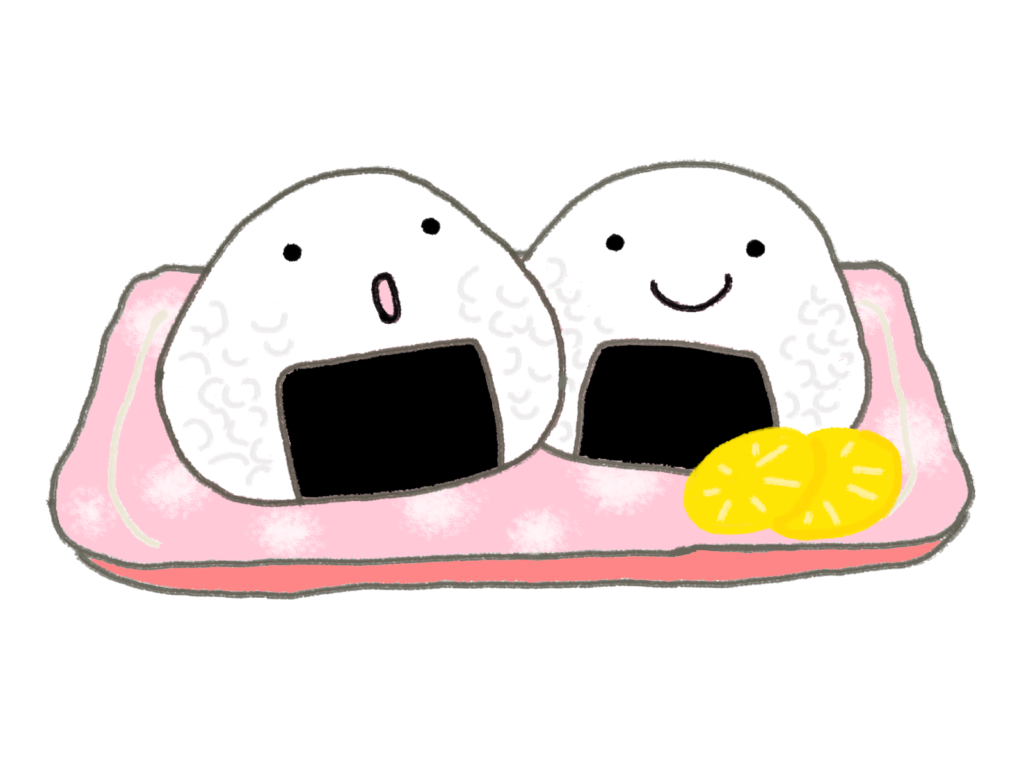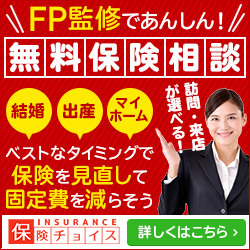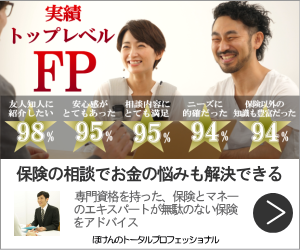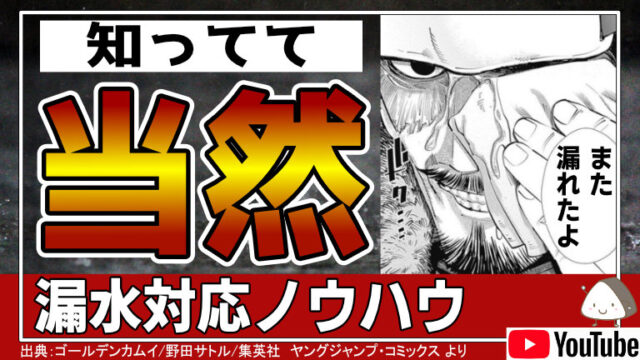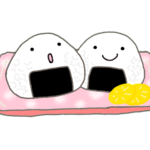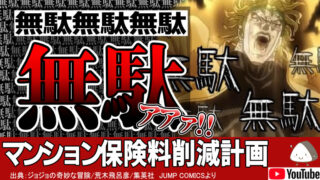「マンションでは漏水が付きもの」
一般の方にはあまりなじみがないかもしれませんが、マンション管理業界では当然のことのように語られており、これを否定する管理フロントはモグリと言ってもいいくらい「マンションあるある」なことです。
前回の記事では、実践的な漏水対応フローについてご紹介しましたが、実は、マンション管理会社の歴戦の勇士でもミスしやすいポイントがあったりします。
今回の記事では、その漏水対応時にミスしやすい重要ポイントについてご紹介します。
はじめに
ちょっと管理会社さん!
ここ、こないだの漏水で濡れたんだけど直してないじゃない!
え”っ、そこって『直さない』って言いませんでしたっけ?
言ってないわよ!水かぶってシミになったんだから、直してくれなきゃ困るじゃない!
「マンション管理あるある」なトラブルの中で5本の指に入るであろう『漏水トラブル』
いざ水を漏らしてしまった(または漏水の被害を受けた)とき、
漏水発生時の大まかな流れ
- 現場確認
- 漏水原因調査(進入口の発見)
- 仮補修(とりあえずの止水)
- 原因箇所の修理
- 被害箇所の修理
このようなスキームで問題解決に取り組む事を以前の記事でご紹介しました。
歴戦の管理会社フロントともなれば慣れたもので、いつものこととばかりに事故処理をしますが、意外と抜けてしまいがちな点があったりします。
今回の記事は、10年以上管理業界に身を置く私が『漏水発生時のミスしやすいポイント3点』についてご紹介します。
この記事はこんな人にオススメ
この記事はこんな方にオススメです。
- 漏水を起こしたことがあり、解決までかなり時間が掛かってしまったという方
- 漏水を起こしたことはないが、どう対応するのか分からない方
- 漏水対応をしたことがない社歴の浅い管理会社フロント社員
- いざ漏水が起こった時、トラブルなく正しい対処ができる
- 漏水対応の方法を体系的に学べる
この記事では、そんな社歴の浅い管理フロントにも理解できるよう、漏水対応を体系的に学べる教材としても作成しています。
ほか漏水関係に関しては▼コチラ▼の記事も是非ご活用ください。

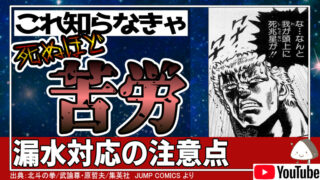
それでは、どうぞ!
『漏水トラブルの対応マニュアル』の結論
簡単に結論をまとめると次のとおりです。
それでは内容について、細かく見ていきましょう。
漏水対応時の3つの注意点!

漏水対応を行う際、いくつか注意点がありますのでご紹介します。
これらを怠るとかなりの重クレームに繋がるので、しっかりと押さえておきましょう。
被害箇所は相互確認にチェック。漏れは絶対あっちゃダメ!
こんな例があります。
漏水発生した当初―――
天井のココと、壁のココが上から漏水してきた場所ッスね。
天井のココの部分も漏水で濡れましたけど、どうします?
まぁ、そこは乾いて目立たないし、どうしようかねぇ?
そうッスか。じゃあ見た目大丈夫ならやらなくていいですかねぇ
こんなカンジで2ヶ月後―――
ちょっと! 天井のココの部分が変色したわよ。
これはこないだの漏水のせいに違いないわ!早くとり替えてちょうだい!
ぇええ! 前の打合せの時に「取り替えない」って決めたじゃないッスか!
私ゃそんなこと一言も言ってないわよ!
こないだの漏水のせいで変色したんだから、取り替えてもらって当然でしょ!私は被害者なのよ!さっさと早く手配して!
さすがにそれはちょっと・・・。
もう修理は全部終わってますし、これから追加ってのも厳しいですねぇ。
このように、漏水の被害箇所を修理する際、その被害部分を曖昧にしておくと、後あと難癖をつけられることが多くあります。酷い例だと―――
最近うちのパソコンが壊れた!
これは半年前の漏水が原因で壊れたに違いない!弁償しろ!
服に染みができてる!
これは1年前の漏水の湿気でカビが生えたのが原因よ!
今すぐ新しいのに買い替えて!
など、どーーーー考えても「それは関係ないだろ」なんて事も、平気な顔して後だしジャンケンのように吹っかけてくる人もいます。
(これはリアルにあった話です・・・。)
そんなことがないよう、『被害範囲(物)』『補償を求める範囲(物)』を被害者側と相互に確認してから補修を行うようにしましょう。
後だしジャンケンにならないためのコツ
- 補修箇所を図面に書いて、被害者と相互チェック
⇒被害者から「これでOK」とサインをもらった方が良い - 水濡れが物品だったら、被害者側からリストを出してもらう
⇒加害者(もしくは管理会社側)から、補償の有無を決めない - 被害者側の水濡れリストができたら、加害者側に了承を取り付ける
⇒漏水被害は原則「加害者側が賠償」
⇒なので加害者側の了承なしに補償範囲を決めてはダメ - 「示談書」を必ず取り付ける
⇒将来補償範囲でトラブルになった時のために
「これでOKしたよね」という書面を残すこと
漏水対応時の『順序』のポイント
漏水の大まかな流れはこのような対応順序となるとご紹介しました。
漏水発生時の大まかな流れ
- 現場確認
- 漏水原因調査(進入口の発見)
- 仮補修(とりあえずの止水)
- 原因箇所の修理
- 被害箇所の修理
ここでのポイントは、『④原因箇所の修理』を先に行い、『⑤被害者側の修理』を後に行うという点です。
漏水の原因が「単にバケツの水をひっくり返した」「洗濯機の蛇口の水が溢れた」という類は別ですが、一般的に『⑤被害箇所の修理』の前に『④原因箇所の修理』をします。
フツーに考えてみれば、なんてことはない当然のことです。
「水道管(下水管)に穴があいて水が漏れた」「外壁や屋上から雨水が浸入した」という場合、漏水の原因箇所をちゃんと直さず被害箇所を先に直してしまうと、また同じことの繰り返しになるので、必ず『原因箇所』を直した後で『被害箇所』を直す、という順になりますよね。
考えてみれば誰でも分かるような事なんですが、しかし、漏水時、特に漏水の被害を受けた方は、これを分かってくれないケースが多くあります。
突然天井から滴る水。
水を被って壊れる家電や家財。
自分は全く落ち度がないのに、自分の部屋や家財が水を被ってずぶ濡れになっていくなど一方的に被害を食らっている最悪な状況。
一刻も早く元通りにしてほしい中、相手から出てきた言葉が
「すぐに直せないので待ってくれ」
そんな事を言われた日にゃ、冷静でいられるはずがありません。
オレは何にも悪くないのに、何で待たされなきゃならないんだ!
いいからさっさと直さんかいゴルァ!
―――っと圧を掛けてくることが結構多くあります。(ホントに多いです。)
人は追い込まれたとき、どんな人も感情的になり、冷静な判断ができなくなってしまいます。
漏水事故なんていう、人生で1度あるかないか分からない希有なトラブルに巻き込まれ、大事な家財を台無しにされたら、多くの人は冷静さを失ってしまいます。
冷静さを失えば、感情論の応酬となり、将来の人間関係に禍根を残すこととなりかねません。
漏水そのもののトラブルより、この人間関係のこじれの方が厄介なトラブルになることもありますので、注意が必要です。
ちゃんと理由を分かってもらえるよう、丁寧に説明しないとね
そのためには、当事者との関係性が重要!
今までどのくらい接点があったかで、相手の態度がずいぶん違ってくるよ。
ここで『初期対応』『マメな連絡』が重要になってくるってワケね!
漏水原因が分からないと保険申請できない!
マンションの漏水事故の備えとして、無くてはならないのがマンション保険。
以前のマンション保険の記事[Link]でもご紹介しましたが、部屋内(専有部分)からの漏水事故の際、多くのケースでは『個人賠償責任保険[Link]』が使われます。
しかし「漏水事故」とひとくくりに言っても、単に「バケツをひっくり返した」「洗濯機から水が溢れた」「給湯機からの給水管に穴が空いた」など、原因が一目見てすぐ分かるものもあれば、『どこから水が来たのか分からない』という、不可思議極まりない謎漏水がマンションではあったりします。
特に築年数が古いマンションなどは、
- 給水管/排水管がキレイに収まってない
- ムダに曲がりくねっている
- 排水管が床下躯体を貫いて下階の屋根裏を通っている
- 配管が全てコンクリート内に埋まっててパイプシャフトから見えない
- 給水管・排水管のほかに、図面には無い謎の管が通ってる
- セントラルヒーツシステム(館内一括給湯方式)のマンションで、全館に給湯管が張り巡らされてる
- しかもそれらが竣工図面に載ってない
こんなことが結構ザラにあり、どんなに調査を重ねても、結局原因が分からず仕舞いなんてことが結構あったりします。
ご存知のとおり、損害保険は「被害額相当の補償をする」という制度です。
しかし、ことマンションの場合「共用部分」と「専有部分」に分かれており、適用される補償内容が次のとおり異なっています。
| 区分 | 所有者 | 適用される補償プラン |
|---|---|---|
| 専有部分 | 個人 | 個人賠償責任保険 |
| 共用部分 | 区分所有者全員 | 施設賠償責任保険 |
つまり、『原因がどこにあるのか(共用部分からなのか、専有部分からなのか)分からなければ、適用される補償プランが定まらないため、保険会社に対して保険申請ができない』ということを意味します。
――っと思ってたら、実は保険申請できる!
ぇええ! じゃあ漏水原因が分からなかったら、保険は使えないの!?
と思っているマンション管理会社のフロントが結構な割合いたりします。
実はそんなことはなく、漏水原因がハッキリしない状況でも保険申請できるんです。
マンション区分所有法には、このように定められています。
第九条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する事項)
建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
引用:建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)
この規定は、漏水などの被害者が損害賠償請求しようとした際、原因が専有部分であればその区分所有者を、共用部分であれば管理組合を相手方に請求します。
しかし「原因がどちらか分からない」となると、被害者の立場から、誰に請求すべきかがハッキリできず、損害賠償請求すらできなくなる恐れがあります。(マンションの漏水の場合『原因不明』となるケースが最たる例です。)
そうしたケースがないよう、被害者救済として「(原因がハッキリしている場合は別だが)マンションの建物から被害を受けたら、その原因は『共用部分にある』とみなすことにするよ」という法律です。
参考:マンションでの漏水事故③(共用部分から漏水が発生した場合)/リビングマガジンBiz
この法律を逆手にとり―――
漏水の原因調査をしても、水漏れの場所を特定できなかった。
なので、区分所有法第九条にもとづき
この漏水は「共用部分からの漏水」として『施設賠償責任保険』を適用する!
という主張で保険会社に申請することができたりします。
このやり方で保険会社に申請して保険会社に保険事故認定をもらったことが実際に何回もあるから、試して損は無いよ!
逆に「原因が分からないと保険申請できない」って管理組合に説明して申請しない方が、トラブルの原因になるかもしれないよ。
自分で勝手に判断せず、保険会社や保険担当によくよく相談しよう!
『原因不明』でも保険申請はできる!
保険が利くか分からなかったらダメ元でも出しとけ!
まとめ!
ここまでの内容をまとめてみましょう。
『漏水トラブルの対応マニュアル』についてまとめると次のとおりです。
言われてみれば「あぁ、何だそんなことか」ということばかりですが、日々追われる業務に並行しながら、スピード、そして居住者対応に神経をすり減らしながら漏水対応を進めていると、案外見落としがちになるポイントだったりします。
しかし今回挙げたケースは、いずれも金銭問題やデカイ重クレームに発展しかねない重要ポイントです。
下手したら「損害を食らった分、管理会社が費用をもて!」なんてムチャを言われることだって考えられます。
そんなことになったら面倒ですよね?
しかし、漏水トラブルは加害者/被害者両方に過度のストレスを与え、議論も感情的になりがちな側面があります。
こういったトラブルを未然に防ぐためにも、押さえるべきポイントは抑え、リスク回避と顧客満足の向上に取り組みましょう。
その心構えについては▼コチラ▼の別記事にまとめていますので、よかったら併せてご覧ください。
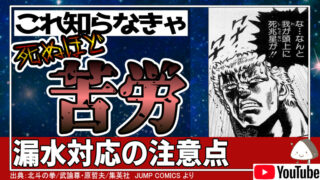
ではこのへんで。かわぐちろろでした。
かわぐちろろ の【ろろ余談】
一番困るのが『原因不明』な漏水。ですが意外と多いんです。
対処療法で修理を繰り返すしかなく、止まったと思ったら数ヵ月後に再発して、出たと思ったらなぜか止まり、以後台風が来ても漏水が起こらない。
これも「マンションあるある」・・・。