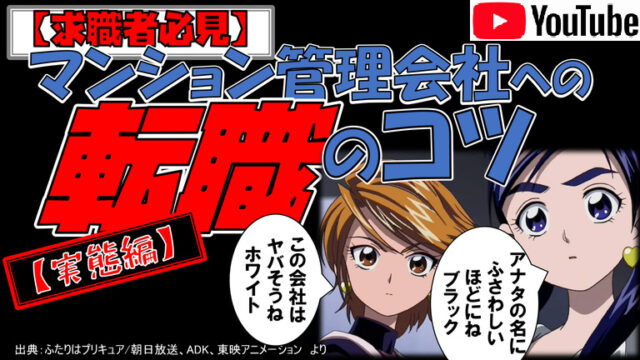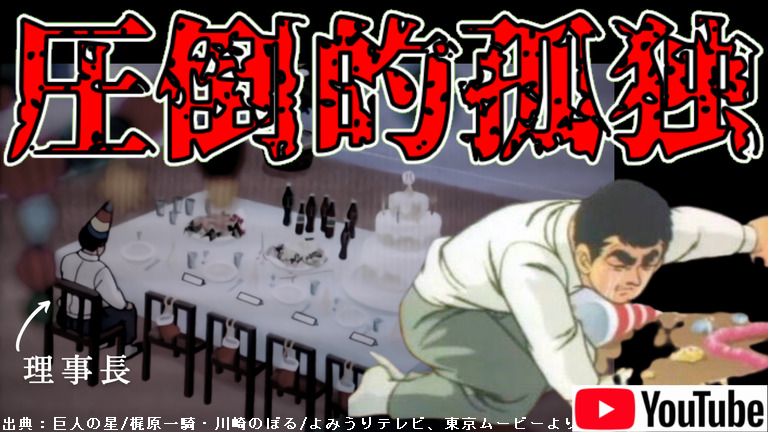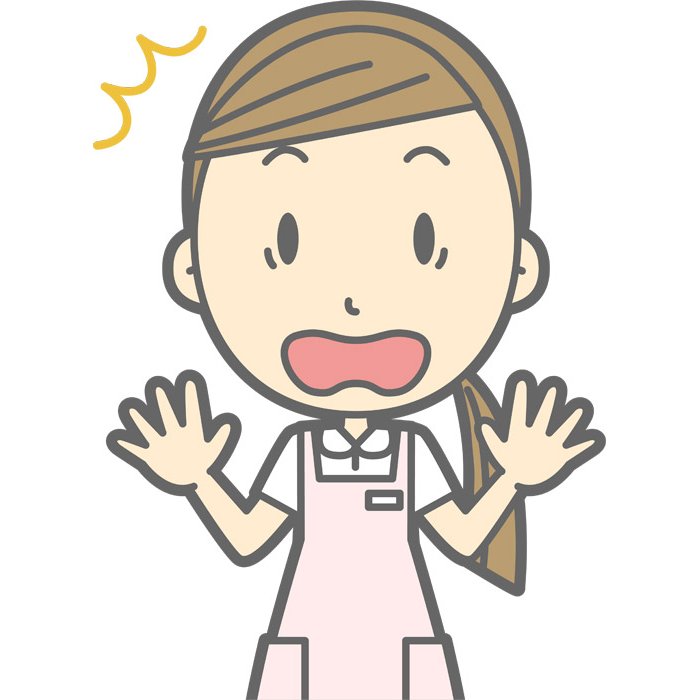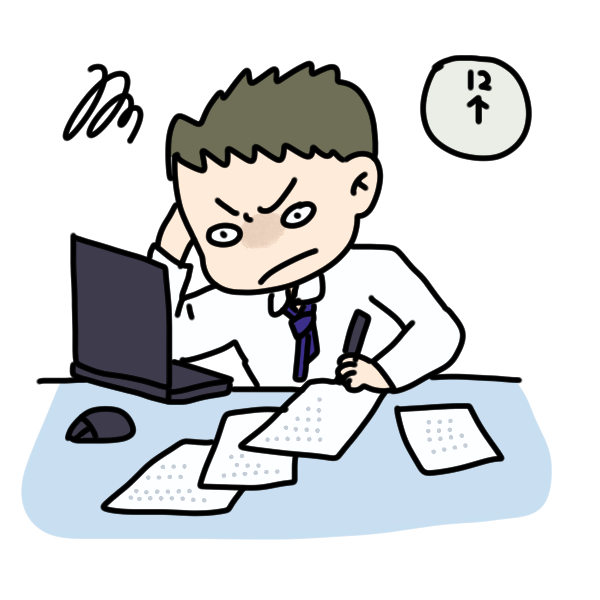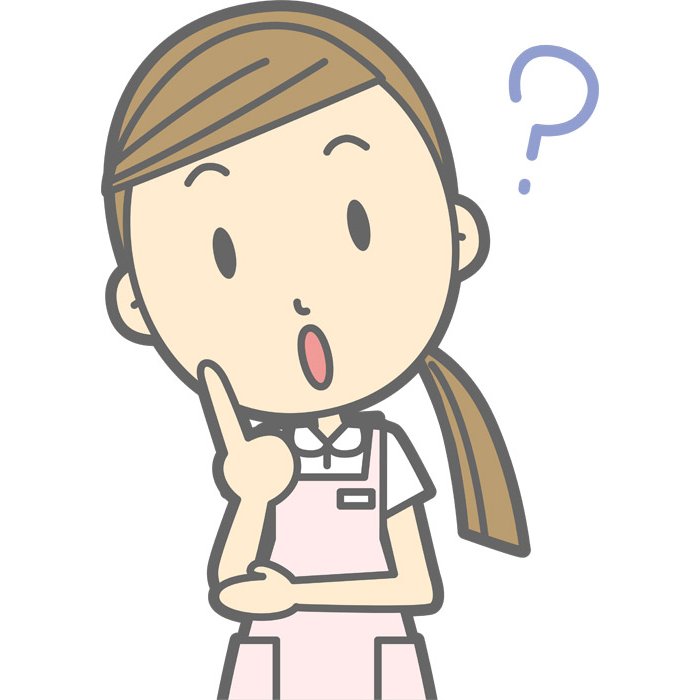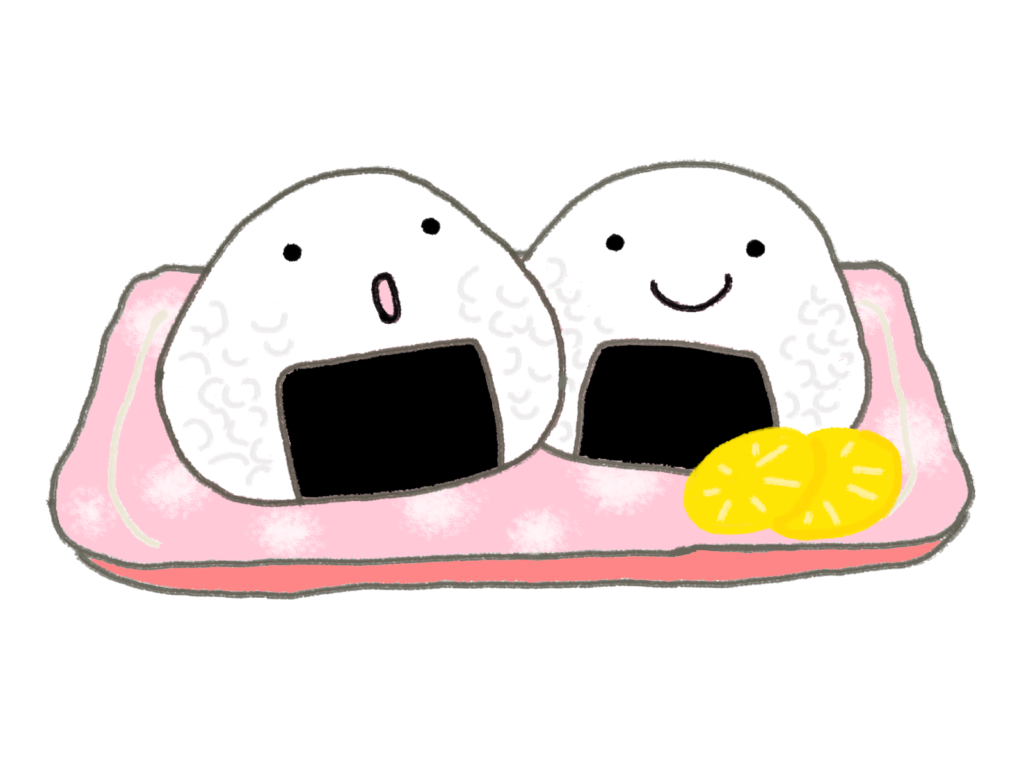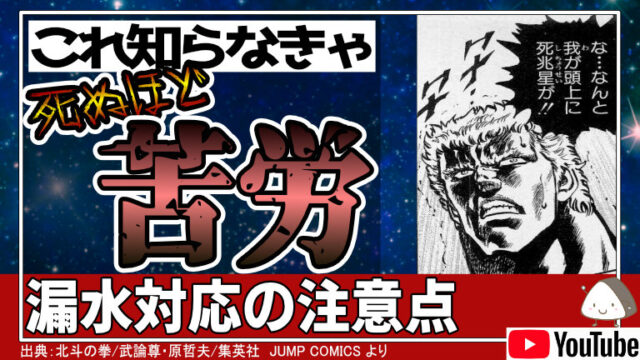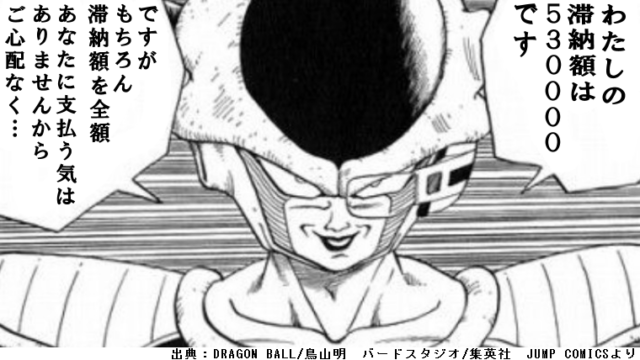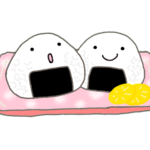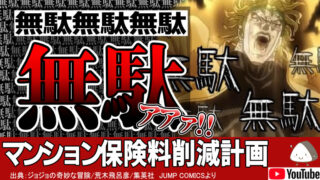はじめに
マンションの総会の時期が近いですし、そろそろ次の役員さんに声掛けしましょうか
私はもう歳だし、役員なんて無理だわよ・・・
何も知らないし無理ですよ、知ってる人がやればいいじゃないですか
仕事が忙しくってできないよ!
~~なんて言われちゃいました。困りましたねー
困ったじゃないよ、そこを何とかするのが管理会社でしょ!
いや~~、そうは言われましても我々には何とも
マンションの役員は、マンション全体のハード面から日常生活のお困りごとのソフト面まで、様々な問題を考え、解決しなければならないお仕事があります。
特に高経年のマンションでは、築浅のマンションと比べ、建物設備などの老朽化により、日頃の管理の課題のほか、さまざまな問題に直面し、マンション管理組合の役員は、その問題に向き合っていかなければなりません。
例を挙げれば
- 居住者の高齢化
- 賃貸率の増加による組合員(部屋の所有者)の不在
- 頻繁に発生する建物の老朽化・設備の経年劣化に伴う度重なる修繕工事
- 築古がゆえの構造上の特異性による修繕難易度の高さ
などでしょうか。
こんな面倒なことはやりたくない。できれば他の人にやってほしい。
そう思っている方も多いかと思います。
そんな中で輪番制で役員を選んでいるものですから、
次の役員の○○さん、前回役員になった時に全然理事会に出てこなかったんだけど、次もそうなるんじゃないの?
△△さん、高齢で持病があるって前に聞いたことあるんだけど、役員に選んで大丈夫なのかしら?
賃貸が多くて、また順番が回ってきたわ。何とかならないの?
という声が次第に多くなり、役員選びがだんだん難しくなっているマンションも多いのではないでしょうか。
マンション理事会役員の方、また管理会社のフロント社員では、
- 役員に選任しても、理事会に出てもらえず、がんばってる役員だけ割を食っている。
- 役員になれる人が少なくて、順番がすぐに回ってくる。
- 役員を「したくない」のか「できない」のか、判断基準が曖昧で、お断りを受けていいのかどうか毎回迷う。
こんなことで悩んだことありませんか?
これまで私が多くの理事会・管理組合のお世話をした中で、毎年役員選びに苦労をしていたマンションは数多くあります。
ですが、ご安心ください!
管理組合の役員や管理会社フロントの負担をなるべくするなくする方法を数多く提案し、実施してきました。
今回の記事は、10年以上管理業界に身を置く私が体験として身に付けた秘策をお教えします。
この記事はこんな人にオススメ
この記事は
- 理事会役員のなり手不足に悩んでいる管理組合の理事会役員の方
- すぐに輪番が回ってきて困っているマンションの一般組合員の方
- 出席理事が少なく理事会の日程調整に悩んでいる管理会社のフロント社員
こんな方にオススメです。
『役員のなり手不足の解決方法』の結論
簡単に結論をまとめると、
このようになります。
これを実践していれば、マンション役員の皆さんにとっても、管理会社のフロントにとっても、理事会役員選びやなり手不足を解消でき、年度末に毎年「来期の役員は~~」と悩む事もなくなることでしょう。
これまでのマンションの歴史、慣例、居住者それぞれの考え方があり、一朝一夕とはいかないかもしれませんが、解決策を見出す一助にはなるかと思います。
それでは内容について、細かく見ていきましょう。
役員のなり手不足 考え方や解決方法について
ここからは、役員のなり手不足のそもそもの考え方や、具体的な解決方法についてご紹介していきます。
なお、『役員とは何?』や『役員ってなにするの?』というかたは、まずはコチラの記事をご覧ください。

まずは現状整理
役員の選任方法について、まずは自分のマンションがどんな決まり(管理規約や総会決議など)の下で決められているか確認してみましょう。
一般的なルールは「マンション所有者であること」
ですが、築十数年以上のマンションでは、「マンション所有者で、実際本人がこのマンションに住んでいること」という条件になっている場合がありますので、ご自身のマンションの管理規約や総会資料で確認してみましょう。
役員に「なれる人」「できない人」をハッキリさせよう
「役員になりたくない」「役員の仕事なんてできない」
役員を断ろうという方は、口をそろえてこう言います。
ですが、それは「やれないと思っているだけ」であって、「やろうとしてもできない」だけかもしれません。
役員にできるかどうか、任せられるかどうか、その線引きをハッキリさせることが必要です。
例えば、
- マンションに住んでいない組合員も役員に入れるか
- 年齢(高齢)は役員辞退の理由になるか
- 病気やケガなどの理由で免除できるか
- 本人に代わって組合員の親族を役員代理にすることはできるか
- 組合員以外の人も役員になれるか
このようなことを考える必要があります。
具体的にはこのような議題で考えるのがよいでしょう。
1.マンションに住んでいない組合員も役員に入れるか
- (役員要件に「マンション居住者」という条件がある場合)マンション外に住んでいない組合員(賃貸オーナー)が理事会に「入ってはいけない」理由はあるか。
これについては
マンションに住んでないもんがマンションのことを知ってるはずがない!そんなもんにマンションの管理などできるものか!
と、言われるケースがあります。
「マンションに住んでいない組合員全員はマンションのことを知らない」などと、不在居=不知と決めつけた全くの精神論では?
と言いたくなりますが、この考えを頑なに持っている方が結構いることにご注意ください。
2.年齢(高齢)は役員辞退の理由になるか
- 高齢者というだけで役員欠格要件となるか
- 高齢者でも元気な方はいるのに、年齢だけを理由に「やれる人」に断る理由を与えていいのか
3.病気やケガなどの理由で免除できるか
- 病気(長期の入院や持病)や身体障害の方で役員就任を断れるか。
- 断れるとしたら、どこを基準にするか。
4.本人に代わって組合員の親族を役員代理にすることはできるか
- 組合員本人が理事会への出席が難しいとき、家族が代わりに役員として活動して良いか。
- 総会で選任された者(組合員本人)以外の人が役員として活動することを、他の組合員は許容できるか。
5.組合員以外の人も役員になれるか
- マンションを所有していない者を役員にしてもよいか。
- どんなものを役員に選べばよいか。逆に選んではいけない者はどんな人か。
「組合員以外の人を役員にする」については、国交省のマンション標準管理規約でも想定されてるやり方だよ。
ただし「マンション管理士」や「建築業者」など、特定の問題を解決するための専門家を一時的にすることを想定してて、「単になり手や人数が足りないから」という理由で選ぶのはお勧めしないよ
具体的な規定例
具体的な規定例をご紹介します。
具体的にはこのような議題で考えるのがよいでしょう。
1.マンションに住んでいない組合員も役員に入れるか
現在のマンション標準管理規約では
第35条(役員)第2項
引用:『マンション標準管理規約(単棟型)』より
理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
というふうに記されており、組合員(マンションの区分所有者)であれば、誰でも役員になるような規定となっています。
過去、国交省では役員のなり手不足の進行を危惧し、役員の要件を「マンションに住んでいる組合員」から、単に「マンションの組合員」と、居住要件を除いて役員枠を広げようとした経緯があります。
マンションに住んでないもんがマンションのことを知ってるはずがない!そんなもんにマンションの管理などできるものか!
という考えを持たれている方も一部でいらっしゃいますが、役員を「マンションに住んでいる者」だけで固めてしまうと、賃貸化が進むとすぐに役員の順番が回ってきて、まさに『なり手不足』に拍車をかけることとなります。
別の見方をすれば、「マンションに住んでいない」という理由だけで「役員になる資格なし」と一方的に決めつけて、一方的に役員の就任資格さえ与えないというのは、居住組合員側の傲慢とも言えるかもしれません。
マンションそれぞれの歴史があり、お住まいの方それぞれの考えがありますので、一概に「これが正しい」というものはありませんが、マンション組合員の皆さんが納得するような理由と、それが通じる根拠を提示した上で、よくよく話し合いの上で決めてもらえればと思います。
あまりにも遠くに住んでいる人は役員活動は無理でしょうから
『生活の拠点が○○県にある場合、または公共交通機関を利用して当マンションまでの移動距離が1時間を超える場合、役員候補者は理事会に対し、役員選任の免除を申し入れることができる。』
という規定をセットで入れる事をお勧めしますよ。
2.年齢(高齢)は役員辞退の理由になるか
「90歳でも現役バリバリで元気な人」もいれば
「65歳でも『こんな歳じゃもうダメ~~』と言い出す人」もいます。
かなり個人事情に左右されるため、年齢だけで一緒くたに考えず、次のとおり『判断能力の低下』『病気や障害』で判断した方がよいと思います。
3.病気やケガなどの理由で免除できるか
- 病気(長期の入院や持病)や身体障害の方で役員就任を断れるか。
- 断れるとしたら、どこを基準にするか。
大病や身体的な障害で役員ができないケースもあろうかと思います。ですが、病気や障害も程度があり、どこまでが認められて、どこまでがダメなのかはっきりさせないと、他の人にも納得考えられないでしょう。
そこで例えば
- 日常生活に支障をきたす程の大病を患っている場合
- 日常生活において介護を要する場合(介護等級が○等級以上など)
というように、ある程度具体的に基準を示したり、基準を決め切れない場合は「理事会が相当と認めた場合」という文言を入れるなど現場判断ができるようにするような規定も有効です。
4.本人に代わって組合員の親族を役員代理にすることはできるか
- 組合員本人が理事会への出席が難しいとき、家族が代わりに役員として活動して良いか。
- 総会で選任された者(組合員本人)以外の人が役員として活動することを、他の組合員は許容できるか。
管理規約では、原則として「選ばれた本人」しか役員として活動することはできません。
ですが、多くのマンションでは
夫が仕事で忙しいので代わりに来ました~
といって、親族という理由だけで理事会に出席したり、平時の業務を行っているケースがあります。
考え方によりけりですが、「そこまで固く考えなくていいんじゃない?」という暗黙の了解で運用されているケースが多いです。
そういう場合
理事が理事会に出席できない場合、当該理事は、その配偶者または一親等内の成年親族を理事の代理として理事会に出席させることができる。
という規定を設け、代理出席をできるようにしても良いかと思います。
5.組合員以外の人も役員になれるか
- マンションを所有していない者を役員にしてもよいか。
- どんなものを役員に選べばよいか。逆に選んではいけない者はどんな人か。
そもそも組合員は、「管理費を払う義務」が課せられ、「マンションが自分の資産」という条件下、『自分の資産をどう活かすか』という観点で役員になっています。
ですが組合員以外の者は「管理費を払う義務」もなく、「マンションが自分の資産ではない」という義務もリスクもない中、果たしてそのような人がマンションのために役員活動をしてもらえるか、よくよく考える必要があります。
こんなカンジで段階的に条件を緩めていくことをオススメするよ
それぞれのマンションの状況に応じて、できること、できないことを話し合いながら決めていきましょう。
まとめ!
役員のなり手不足は、
- 「なぜなり手が不足しているのか」「本当にできない」のか、それとも「やりたくないだけなのか」を見極めること。
- 「できる人」「できない人」を区分けして決まりを作ること
- 必要に応じて枠を広げること。
この3つを把握していけば、幾分なり手不足は解消していくでしょう。
それでも役員になるのは不安だわ・・・
という方もおられると思います。
その場合は管理会社を頼って、自分は何をすればいいのか、どう役員として立ち振るまったらいいのか聞くのがいいでしょう。
そのために管理会社がいるのですから。
ではこのへんで。かわぐちろろでした。
マンション管理士かわぐちろろ の【ろろ余談】
役員は手間がかかりますし「できれば他の人にやってもらいたい」と考えがちですが、自分の持ち物を自分でメンテナンスすることは、至極当たり前なことです。
『自分のマンションをどうステキにするか』
そう考えれば、少しはやる気が出ませんかね。